※性描写があるので18歳未満の人はみちゃだめです。
あとなんだかシュタデスだけどリバっぽいから気になる人はちゅうい
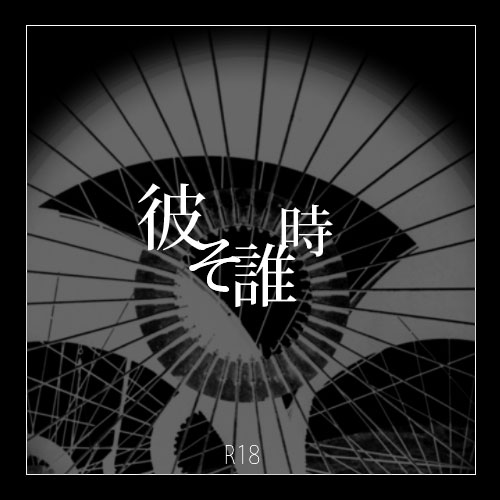
「お前ばかり上というのはいかがなものなのか」
「・・・・・・・・はい?」
「いつもいつもお前ばっかり男役でずるい。お前きもちぃだけじゃん。俺は大変なんだよ」
「・・・・・・でも先輩さっきすごい声出してもっと欲し「黙れ」
先輩はごほん、と咳払いをした後短くなった俺から途中で奪って吸い始めた煙草を灰皿に押し付けた。最後の香りが立ち上る。
「・・・・・・・・とにかくお前ばっかりずりいんだよ。もう少しつっこまれるほうの身にもなってみろ。そうだお前はつっこまれるほうの気持ちがわかってない。そんなんじゃもてないぞ」
「俺先輩にもてればそれでいいんだけどな」
「残念ながらそれはない。そんなわけで一発ヤらせなフランケン=シュタイン」
そんなわけでが接続詞の用法として間違っていると思うのだがそんな思索にふけっているうちに先輩は俺の上にのしかかって動きを封じに来た。膝の関節の上に痛まない程度に体重をかけ俺の両肩の横に肘をついて覗き込んでくる。いつも俺が先輩にやる方法だった。まったくこういう事ばかり覚えが早い。
すごい状況になってしまった。事後の乱れたシーツの上でお互い何も身に着けていないこの状況で。
いきなりさっきまで好き放題にいじめ倒した相手に逆転され、しかもその相手は俺に報復する気満々と来た。女の子でいうところの「身の危険を感じる状態」だ。時刻は午前四時をまわったところ。日の出の予感に何もかもが不安な程真っ青に染まる世界にエラーが起こったような時間帯だった。
先輩は至極まっとうにまじめくさった顔で俺を覗き込んでくる。どうやら冗談のつもりはないらしい。
「お前むかしは本当にかわいい顔をしていたんだけどな。病弱ないかにもか弱そうな女の子みたいだった。
んで話しかけてみたら中身は最悪だったけどな。」
「死武専に入って俺に事務的なこと以外で話しかけてきたバカは先輩が初めてでしたよ」
「・・・・・・・・・・・・・・バカって・・・・・・・。今だって黙ってりゃわりと美人なのに。」
俺がへらりと笑ったら先輩は顔をしかめてその笑い方もやめな、といった。そして俺の顔の縫い傷をぬらりと舐めた。
唇にやわらかい感触がする。ふに、ふに、と何回か来たあと唇の端の頬とも唇とも言えない箇所にキスがきてそれから唇を薄い舌が左から右へなぞった。思わず開けるとムースのような舌触りのきめの細かい先輩の舌が入り込んでくる。俺の好物だった。
たださっきまで煙草を吸っていたのでニコチンとタールと一酸化炭素の味がする。俺も多分同じ味だ。
一通り絡めたあと軽く最後に舌を吸われてついでに上唇を甘噛みしてから先輩はキスをほどいた。
なるほどこれでいつも女の子をめろめろにしているわけか。
角度を変えてもう一度きて口蓋の上をなぞられたときは思考が溶けて目を細めた。
でもなるべくキスしている先輩は見逃したくなかった。だってとても格好いい。
うなじのところから耳の後ろあたりまで先輩が指を差し込んできて髪の毛をさわる。俺も先輩の脇腹から腰、お尻まで撫でる。ぴくりと先輩の足が跳ねた。受身なのもなかなか悪くないかも知れない。与えられる錯覚というものは総じて気持ちがいい。
何回か角度を変えてキスをした後ゆっくり先輩が離れた。深いため息みたいな息継ぎをする。
目が離せなくてお互いなんだか照れてしまった。
「な?俺のほうが巧いんだって」
先輩がちょっと得意げに言って自分の上唇を舐めた。そりゃこんなに巧くなるまで遊んだら離婚もされますね。
長くて綺麗な指が俺の手に絡まってきて口元に寄せられ指の間を舌で愛撫した。うわこの人こんなことするんだ。思わず腰が疼いた。俺の動揺を悟ったのか先輩は優位を確信し小悪魔めいた顔をした。
ゆっくり姿勢を低くして胸に手を這わせたあと触りながら腰骨にキスを落とした。
シーツがするすると秘密めいた音を立てる。そうして段々したに下がっていって疼きの中心に指を絡めて唾液を落とし何回か掌で上下に動かす。
思わず体がこわばる。先輩がためらいなく舌を這わせてきた。少し声を出してしまった。 いつも先輩にそうさせているときにやるように頭をつかんでやわらかいその髪の毛を弄る。
口に含んでいる質量が増したのか先輩がちょっと苦しそうに眉根を寄せる。どうしようすごくきもちいいなぁ。じんじん痺れてきた。
「・・・・・・・・・・・・ねえ、せんぱ、い」
「・・・・・・・・・・」
「ねえっ、て、ば」
きゅ、と髪の毛をひっぱったら不満そうに唇を離した。唾液と他いろいろなもので唇がてらてらひかっている
「せんぱい俺に入れるの」
「おうよ」
「せんぱい俺に勃ってんの」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・・・・・・先輩?」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
たっぷり2分は間があったと思われる。
先輩は今気づいたという顔をして、そして思いっきりしまった、という顔をした。
・・・・・・・やっぱりその辺を考えてなかったかこの人は。
ついでなのでつついて遊ぶことにする。彼のプライドというおもちゃを。
「へぇ・・・・俺に付き合わされて無理矢理だと思ってたんですけど・・・・・そうでもなかったんですね・・・・生粋の女好きかと・・・・ふうん・・・・・ついに男にたつように・・・・へぇ・・・・・」
「〜〜〜〜〜〜〜〜〜っっ!!ちが・・・・・っ!」
先輩は髪の色と同じくらい真っ赤になった。あんなにかっこよくて悪魔的な色気に満ちていたのにどこへいったのやら。
きょどきょどと視線が右往左往してあろうことか逃げようという体勢をとった。逃がすものか。
「ぎゃあ」
がっちりと二の腕をつかんで引き寄せる。バランスを崩して俺の胸のあたりに密着することになる
「これ、どうしてくれるんですか」
屹立を先輩の股の下、スリットに沿って深くこすり付ける。ぬちゃりと粘液が滴る音がして先輩が恥ずかしさに身を震わせる。
もう先輩がどうなのかはとっくの昔にわかってしまっている。わかっていてあえて寸前まで何も言わなかった。言い訳を作る隙を与えたくなかったから。なんとしてもこの関係を一時の気の迷いと定義して認めない、自分にいっさいの過失はないと信じたい先輩の逃げ道を塞いで追い詰めるために。
なんなら本当に抱かれたってかまわない。俺はそんなどっちがどっちにとかは気にしない。たとえ先輩が女でも同じことをしただろうし。これはたまたま性別が同じだった結果だ。先輩と出来ればそれでいい。まあこの結果はやや予想外だけど。
俺は先輩が男でも女でもたつ自信があるけど先輩が俺にたつのは彼の嗜好上無理だろうなと思っていた。
そして先輩がここまで考えてなかったとは思わなかったし、ここまで動揺するとも思わなかった。
「先輩どうする?俺先輩に入れられるのでもぜんぜんかまわないんだけど」
「・・・・・・・うー・・・」
「このままおしまい、はナシね。俺それ無理だから」
また腰を動かす。ぬち、と粘着な音が響く。
「ばか!」
先輩は困ったと怒ったの中間みたいな良くわからない顔をする。彼のあまり出来の良くない頭で葛藤しているのがわかる。進むのも退くのも彼にとっては何かしらの負けを意味するのだろう。俺はどう転ぼうが楽しめる。
オレは先輩にばかといわれるのが結構好きかも知れない。いやばかと言ってる先輩が好きなんだろうな。
バカにバカにされる事ほど腹の立つことはないが先輩だとその法則は当てはまらない。
ほかにも先輩は俺の法則をたくさん打ち破る力を持っている。
ぬるぬるになった内腿に指を這わせるとぎゅっと目を閉じてその紅い睫毛を震わせる。耳があるとしたら完全に伏せられてふるえているかんじだ。どうしよう。受身でいるつもりだったけどひどいことをしたくなってきたなあ。
「せんぱいのいくじなし」
「うるさ・・・・ぁっ!?」
ぐっと割りひらいて先端を押し込む。2回目なのでまだそこはやわらかく濡れていた。
「ぅ、あ、あぁ、やだ」
上に乗っているので自重でどんどん俺の欲望の侵入を許してしまい先輩は怖がった。先輩が怖がったり泣いたりすると俺の中で昏い感情が湧き上がる。
いつまでも生娘のように怖がるくせに体のほうは意に反してひくひくと貪欲に俺を銜え込んでいく、そのギャップがたまらない。
先輩自身もこの理性と本能のズレに体を扱いあぐねているのはわかる。
大丈夫、すぐそんなのわからなくしてあげるから。
「ぃて・・・・ちくしょ・・・・ぅ」
あまり触ってなかったから一度に全部は入らなくて先輩が苦しそうに息を吐く
少し間をおいて目を閉じ、息をゆっくり吐いて腰を沈めてきた。毎度毎度この包まれる感じは強烈な眩暈を伴う。
俺も目を閉じて息を吐く。顔がみたくて指でカーマイン色の髪の毛を触り耳にかける。目が合う。
「先輩動いてね、今回先輩が上なんでしょ」
ぺち、と叩かれた。ばか、とかしね、とかちがうとかだまされたのなんの知性の欠片もない反論をするので下から思いっきり突いてやったら心底悔しそうな顔をされた。
その後座ったりひっくりかえしたりしていろんな角度でいじめていたら夜が明けた。
一応主人に反逆しようとした飼い犬はしつけとかないとだからね。そういう意味でもわりとしつこく泣くまで。
案の定先輩はものすごく機嫌を損ねた。
つぎはぎのはいったちょっと大きいシャツを羽織ってぶすっとした顔でいすに座っている。
そのかっこうは目に毒だから下に何か履いてほしいといつも思うんだが。
ガーリックバタートーストと生ハムとルッコラのサラダに生クリーム入りスクランブルエッグを皿に追加する。
先輩は俺のもつフライパンになんとはなしに注意しながらおもしろくなさそうにサラダの輪切りオリーブをつつく。
「・・・・・・・・・やっぱりお前ばっかりが楽しいじゃん。ずるい・・・・・・・。」
「先輩も充分楽しんでいたような気がしましたが」
キッチンにフライパンを戻し自分の分のコーヒーをコーヒーメーカーから注いでダイニングに戻る。皿は確か蒸発皿の何号かだったような気がするけど黙っておこう。
「そうゆうことじゃねぇよ。大体テメェ人がもういいって言ってんのにしつこく・・・・」
「イワン・パブロフと同じことをしたまでです」
「あ?なにそれいみわかんね。 とにかく 次は俺のばんだからな!」
危うくコーヒーを吹き出しそうになった。
「…・・・・・こりないですねせんぱいも・・・・」
「んだよそのバカにしたような目線は。俺だってやるときゃやるぜ」
「めちゃくちゃヘタレてたじゃないですか・・・・・・・・」
るせ。先輩はちょっと照れたみたいに顔をそらしてバタートーストをかじった。
朝の先輩は本当に何もしない。王様みたいにいすにふんぞり返ってさも当然のように朝ごはんが出てくるのを待つ。そしてまったく何の感謝もなしにそれを食べる。そういうところに彼の誰かと共に住んだ期間が長いところが出る。与えられることに慣れている。
「期待しています」
「おうよ。絶対オメーを泣かしたる」
「あはは、俺先輩ほど涙腺弱くないから」
どうやら外は快晴のようだった。シーツを干したら少し出かけてみようかな。
こういうのを一般的には幸せって言うのかな。俺には縁が遠すぎてよくわからないけど。
これを幸せと名づけてみよう。すべては自己の認識の問題だ。陳腐だが悪くない。
2009/03/01 ZERA